【教員が語る!専門分野と研究室紹介 vol.4】~食品プロセス学研究室編~
- #大学の先生
- #教員が語る!専門分野と研究室紹介
- #研究室
こんにちは!健康栄養学科です。
教員が語る!シリーズ第4弾となる今回は、
食品プロセス学研究室の稲垣先生です!
①研究室名・分野紹介―食品プロセス学とは?
「プロセス」とは、食品用語で「加工」という意味です。食品の材料となるものはもともと自然のなかにある植物や動物ですが、人の手による修飾(加工)が加えられて「食べ物」になります。古来からの加工の目的は「保存」です。そのおかげで、現在のように「食べたいときに食べたいものを食べる」ということができるようになりました。それ以外にも、「よりおいしいものにする」「食べやすくする」「健康に良いものにする」など、加工の目的が増えてきています。食品プロセス学は、そのような目的を達成するための加工方法や加工による成分の変化などを詳しく学ぶ学問です。
.jpg)
②主な担当科目(専攻|年次)
食品プロセス学(管理|2年)
食品プロセス学実験A(管理|2年)
食品プロセス学実験B(管理|3年)
食品プロセス学(食物|3年)
食品機能学(管理・食物|3年)
③卒業論文で扱っているテーマについて
食品プロセス学研究室の卒業論文では、加工食品のうち発酵食品、特に「納豆」に着目しています。納豆にはイソフラボンやビタミンK、ナットウキナーゼなど、とても健康によい成分が含まれていることがわかっていますので、多くの方に食べてほしい食品ですが、独特の臭い(納豆臭)があるため食べることを敬遠するひともいます(特に関西では!)。せっかく加工の技術で健康によいものにしても、一つの欠点によって食べることができないのはとても残念ですよね。そこで、昨年度は「納豆臭の軽減を目的とした新規納豆の開発」というテーマで1年間、卒業研究に取り組みました。
東北地方には五斗納豆という食べ物があるのですが、この食品はひきわり納豆に米麹(こめこうじ)を加えてひと月ほど冷蔵庫に置いておくことで、納豆とは全く異なる(納豆臭のない)風味になったものです。この五斗納豆の製造方法を参考に(応用)して、簡便な方法で納豆臭の少ない(またはない)新しい納豆を作り出すことができないかを検討しました。

④その他学内外での研究や活動について
すこし専門的な話になりますが、③以外の研究として、「納豆におけるイソフラボンのアグリコン化に関する研究」というテーマでも研究を行っています。大豆には骨の健康などによいと言われるイソフラボンが豊富に含まれていますが、大豆に含まれる形のままでは効果が弱く、アグリコン型という形に変換されることで高い作用を発揮することがわかっています。味噌や醤油などの発酵食品にはアグリコン型のイソフラボンが多く含まれていますが、納豆にはほとんど含まれていません。そこでこの研究では、納豆にアグリコン型イソフラボンが少ない理由を解明することや、それらを豊富に含む納豆の開発を目指しています。
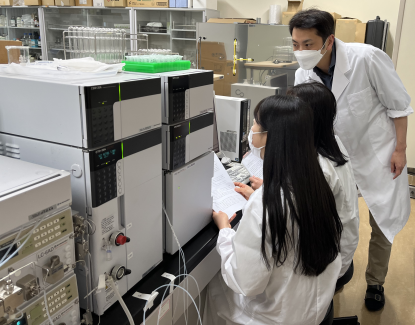
⑤栄養士・管理栄養士を目指す高校生(学生)に、この分野の重要性やアピールポイントを教えてください!
食事は人々が毎日欠かさずに行っていることなので、食品について詳しく学ぶことは、普段の生活をとても楽しいものにしてくれます。管理栄養士を目指す方にとって食品プロセス学はその入り口で学ぶ科目(基礎分野)ですが、将来、とても広い分野で役に立つ知識になります。まずは自分の好きな食べ物に注目して、「どのように作られているのか?」「健康との接点は?」などについて考えてみてください。きっと、食品への興味がふつふつと湧いてくるはずです。

関連情報
RELATED 関連記事
学科カテゴリ
アーカイブ
最新の記事
- 8月24日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~
-
8月24日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~
- 美容コース学生有志によるヘアドネーションイベント-no.9-
-
美容コース学生有志によるヘアドネーションイベント-no.9-
- 8月10日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~
-
8月10日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~
- 化粧ファッション学科卒業研究中間発表会
-
化粧ファッション学科卒業研究中間発表会
- 7月20日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~
-
7月20日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~


