【教員が語る!専門分野と研究室紹介 vol.1】~応用栄養学研究室編~
- #大学の先生
- #教員が語る!専門分野と研究室紹介
- #研究室
こんにちは!健康栄養学科です。
教員が語る!シリーズ、
第1弾は、応用栄養学研究室の青先生です!
①研究室名・分野紹介―応用栄養学とは?
栄養学という学問は、様々な分野を含んでおり、このブログシリーズでこれから紹介していくように、大学にはそれぞれの分野の研究室があります。
大きく分けると、食品を研究する分野、メカニズムを研究する分野、実際のヒトでの利用方法を研究する分野があります。
応用栄養学は、「実際のヒトでの利用方法を研究する分野」に当てはまります。
つまり、「ある栄養素は〇〇の働きがある」を明らかにするのはメカニズムの研究ですが、応用栄養学は、「じゃあ結局1日にどのくらい摂取すればいいの?」を研究する分野です。
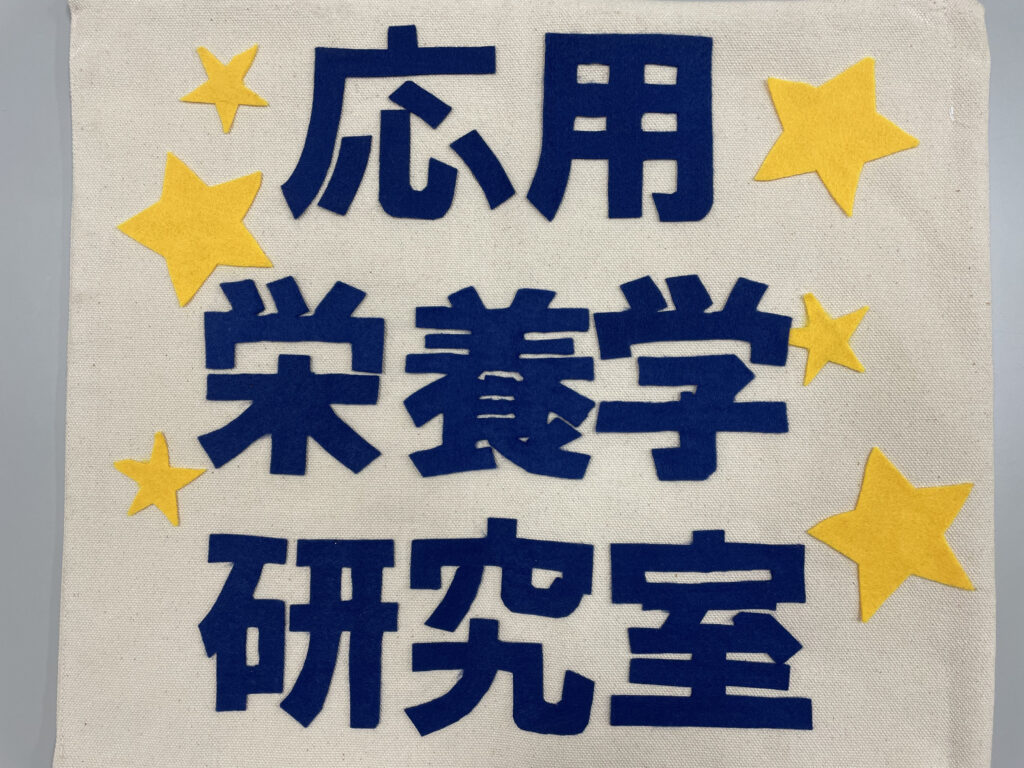

摂取すべきエネルギー量や栄養素量を考えることは、栄養管理をするということ。
栄養管理の内容は、もちろん様々な要因によって変わります。
授業では、基礎となる栄養管理方法、ヒトが摂取すべきエネルギー量と栄養素量についてのエビデンス、各ライフステージ・環境別の栄養管理方法について教えています。
②主な担当科目(専攻|年次)
栄養マネジメント実習(管理|2年)
応用栄養学A(管理|2年)
応用栄養学実習(管理|2年)
基礎栄養学(食物|1年)
生化学(食物|1年)
③卒論で扱っているテーマについて
現在の栄養学は完全ではなく、実はまだまだ明らかになっていないことが多くあります。
健康を維持していくために必要なエネルギー量と栄養素量の包括的なガイドラインは、
「日本人の食事摂取基準」ですが、疾患との関連が明らかになっていても、「どのくらい摂取すべきか」の研究結果が揃っていない部分があります。
私はこれまで一貫して水溶性ビタミン(特にビタミンB1、ビタミンB12)の栄養状態と疾患との関連を研究してきました。私が知りたいことは、「ヒトの健康のために必要な摂取量が長期的に不足することは、様々な疾患リスクを増加させているのではないか?」ということです。栄養素であるビタミンは薬剤とは異なり、その摂取の結果は長期的な健康に影響します。今日少し足りなかったとして、明日すぐに何か症状が出ることは稀ですが、長期的に必要量が不足している食生活は種々の疾患リスクを増加させている可能性があります。
まずは、栄養素本来の役割を考えて、習慣的な摂取量が疾患リスクに影響を与えていないか、さらに疾患リスクを増加させないために必要な摂取量はどのくらいなのか、を明らかにするための研究結果を出したいと思っています。特に日本人を対象としたこのような研究結果は、実は意外と乏しいのが現状です。そこを明らかにするために、研究をしています。
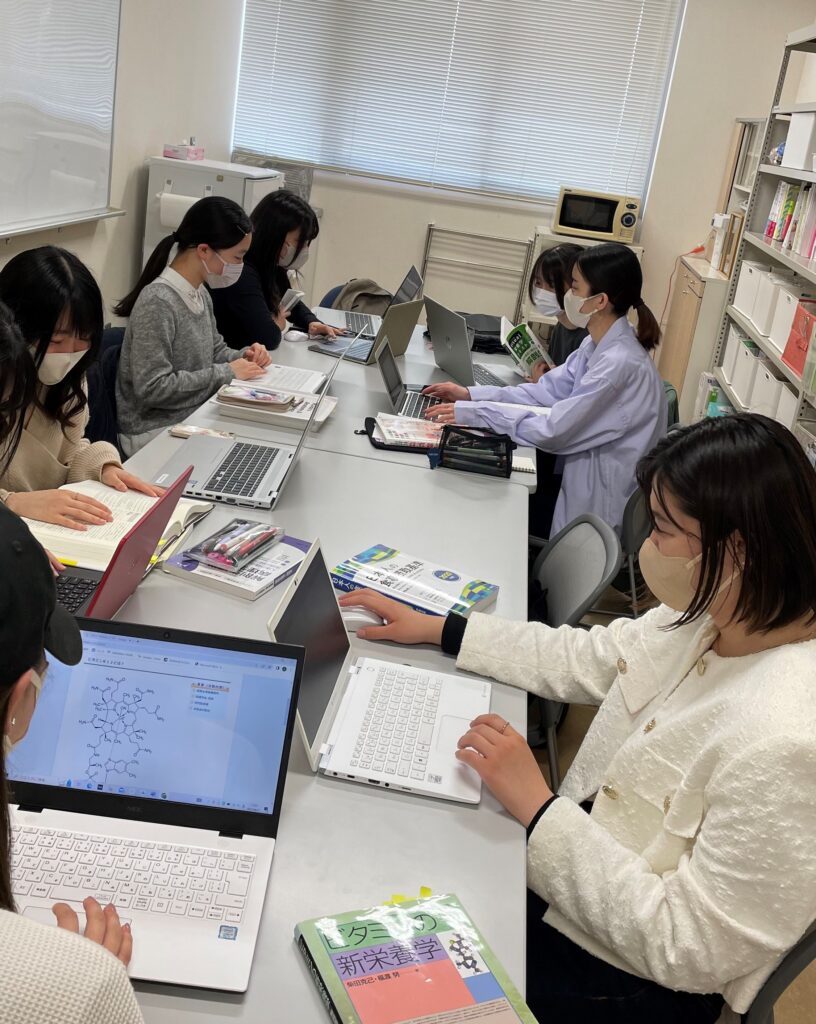
④栄養士・管理栄養士を目指す高校生(学生)に、この分野の重要性やアピールポイントを教えてください!
栄養士・管理栄養士は、栄養の話をする際に料理レベル、食品レベル、栄養素レベルの全ての段階で考えられる能力が必要です。一般の人が最も馴染みやすいのは料理レベル(お味噌汁、サラダ…)ですが、料理は食品(豆腐、レタス…)を使って作られ、食品には栄養素(たんぱく質、ビタミン…)が含まれています。応用栄養学分野の授業では、ライフステージ別の必要な摂取量を栄養素レベルで考え、その摂取量を実現するための献立を考えます。栄養士・管理栄養士として働く際に必要な知識と実践を取り扱う分野です。
ぜひ一緒に学び、研究しましょう!

関連情報
RELATED 関連記事
学科カテゴリ
アーカイブ
最新の記事
- 8月24日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~
-
8月24日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~
- 美容コース学生有志によるヘアドネーションイベント-no.9-
-
美容コース学生有志によるヘアドネーションイベント-no.9-
- 8月10日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~
-
8月10日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~
- 化粧ファッション学科卒業研究中間発表会
-
化粧ファッション学科卒業研究中間発表会
- 7月20日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~
-
7月20日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~


