【教員が語る!専門分野と研究室紹介 vol.16】~運動栄養学研究室編~
- #大学の先生
- #教員が語る!専門分野と研究室紹介
- #研究室
皆さんこんにちは、健康栄養学科です🏃♀️
夏にわたってお届けしてきた教員が語る!シリーズ。
いよいよ今回が最終回となります!涙
トリを務めさせていただきますのは、運動栄養学研究室の角谷先生です!
①研究室名・分野紹介―運動栄養学とは?
実は「何を、どれだけ、いつ食べるとよいのか?」といった問いへの回答は、個々人にとって異なります。この個人差を説明する要因はさまざまあります。
代表的なものは、年齢、性別、妊娠・授乳、ストレス、気温などの環境、そして運動を含めた身体活動です。特に、運動は身体に大きな変化をもたらして、「何を、どれだけ、いつ食べるとよいのか?」に影響を与えます。
例えば、日々たくさんの運動をしているスポーツ選手は活動的ではない人と比べて、必要なエネルギー(カロリー)が約2倍になることもあります。2倍のエネルギー(カロリー)を補う食事を考えるのはなかなか難しいものです。
運動栄養学は、主に以下の3つの問いに挑む学問分野です。
①運動が「何を、どれだけ、いつ食べるとよいのか?」にどのような影響を及ぼすのか。
②運動によって増加した必要なエネルギー・栄養素量をどうやって補うのか。
③スポーツにおけるパフォーマンスを向上させるには「何を、どれだけ、いつ食べるとよいのか?」。
運動栄養学は、運動と栄養の相互作用を捉える必要があるため、運動生理学やスポーツ医学など広い知識の求められる学問です。
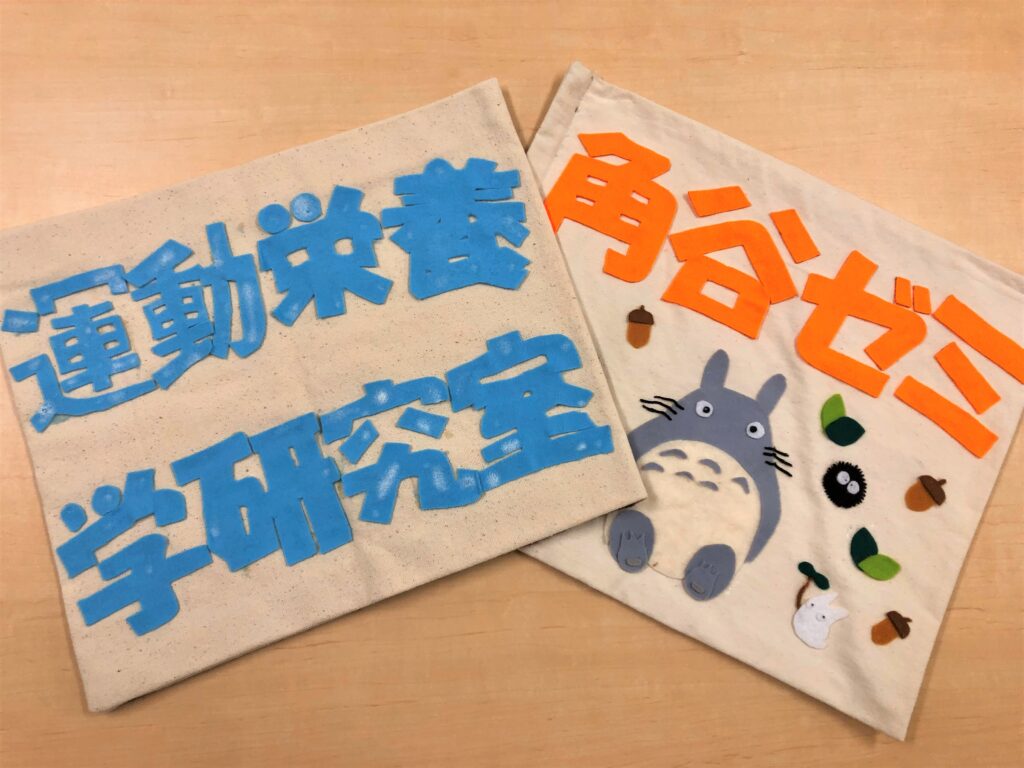
②主な担当科目(専攻|年次)
栄養マネジメント論(管理|1年)
栄養マネジメント実習(管理|2年)
応用栄養学B(管理|2年)
応用栄養学実習(管理|2年)
応用栄養学A(食物|1年)
運動栄養学(管理、食物|2年)
運動栄養学実習(管理、食物|3年)
③卒業論文で扱っているテーマについて
中高生の審美系スポーツ選手を対象に行った体組成・骨の測定や食事調査の結果をもとに、次のような卒業研究に取り組んでいます。
・スポーツ選手にとって望ましい栄養素摂取に繋がる「食べかた」とは?
・骨の成長と関連する「食べかた」の探索
・月経異常と体格の変化との関連
-1024x780.png)
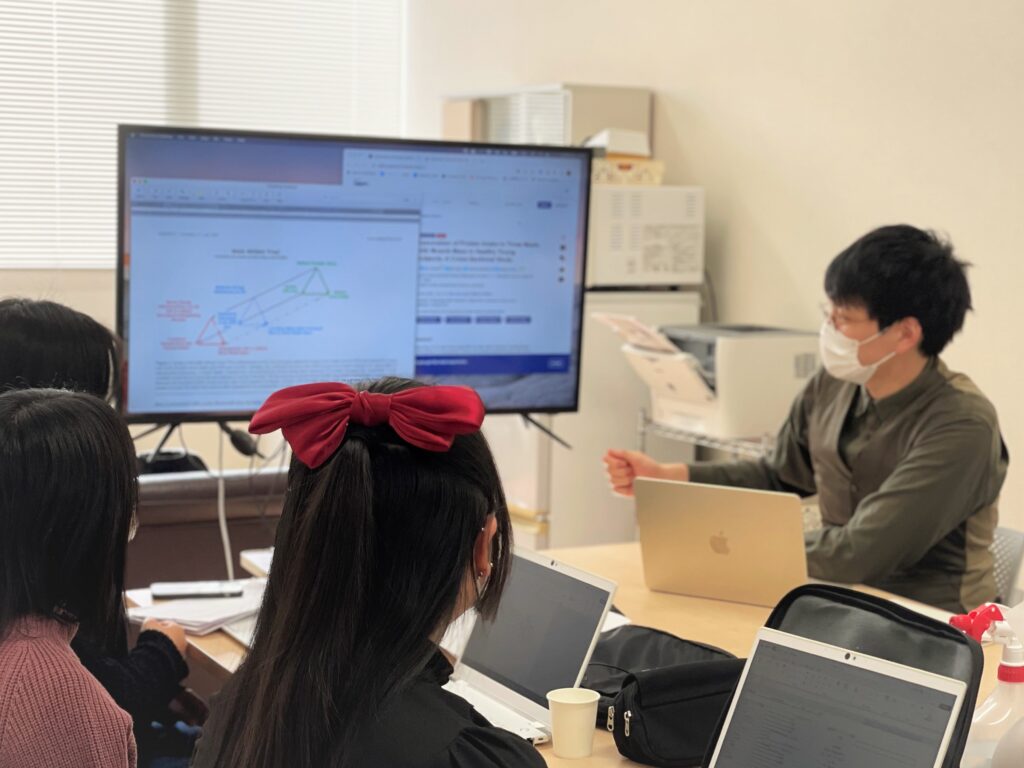
今年度は上記以外にも、市場に出回っているスポーツドリンクの成分比較に関する研究や、運動栄養分野の教科書・書籍に関する文献調査に取り組んでいます。
④その他学内外での研究や活動について
樟蔭中学・高校と連携して行われているShineプロジェクトの一環として、健康栄養学科の学生を中心に活動している、「Shineスポーツ栄養研究会」の世話人をしています。
Shineスポーツ栄養研究会の活動に関しては、過去の学科ニュースでも何度か取り上げられていますので、興味がある方はそちらをご覧ください(関連ニュース)。
研究会に参加してくれている学生にはこの活動を通して、“主体的に学ぶ姿勢”を身に付けてほしいと考えています。なので、こちらからの積極的な指示はあえて行わず、学生たちが自分で考え協力し、情報を取捨選択したうえで責任をもって情報発信やレシピ提供を行えるようなサポートを心がけています。

(▲Shineの活動の様子)
また同じくShineプロジェクトの一環で、樟蔭高校の身体表現コースの生徒に年2回の特別講義を開いています。さらに2022年度からは、外部の高校の部活動に出張スポーツ栄養セミナーも行っています。スポーツを行う高校生に、栄養学について興味を持ってもらうきっかけになればと思います。
⑤栄養士・管理栄養士を目指す高校生(学生)に、この分野の重要性やアピールポイントを教えてください!
栄養学の領域では、生活習慣病の治療に代表されるように、マイナスな状態をゼロに近づけるという事例を扱うことが多いと思います。そんな中、運動栄養学分野では、今の状態からさらにパフォーマンスを上げる、プラスにするために、「何を、どれだけ、いつ食べるとよいのか?」について考えます。「これを食べると誰でも走りが速くなります」なんて魔法のような食べ物はもちろんありませんが、食に対する意識・行動を変えることがパフォーマンス向上に繋がるなら、それを探ってみたくありませんか?
ぜひ大阪樟蔭女子大学で、一緒に運動栄養学を学びましょう!

関連情報
RELATED 関連記事
学科カテゴリ
アーカイブ
最新の記事
- 8月24日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~
-
8月24日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~
- 美容コース学生有志によるヘアドネーションイベント-no.9-
-
美容コース学生有志によるヘアドネーションイベント-no.9-
- 8月10日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~
-
8月10日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~
- 化粧ファッション学科卒業研究中間発表会
-
化粧ファッション学科卒業研究中間発表会
- 7月20日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~
-
7月20日オープンキャンパスを開催しました~化粧ファッション学科~


